スケート
みなさん、こんにちは![]()
まだまだ寒い日が続きますね![]()
先日、子どもの保育園行事で福山メモリアルパークの
スケート教室に参加してきました!
福山メモリアルパークには新幹線が臨める広い公園があり![]()
夏はプール、冬はスケートが楽しめる子どもたちに
とても人気のスポットです![]()

スケートのリンクに立とうとすると
あっちでコロコロ![]() こっちでコロコロ
こっちでコロコロ![]()
見事に転がっていた子どもたちですが![]()
徐々にちょこちょこ滑れるようになっていました![]()
私も一緒に滑ったのですが、
子どものころ以来○十年ぶりのスケート…
手すりから離れられずでした![]()
一般のお客さんもいて、中にはフィギュアスケート選手
のように華麗に滑っている方もおられました。
憧れます![]()
 みなさんも近くにお立ち寄りの際には、
みなさんも近くにお立ち寄りの際には、
ぜひ訪ねてみてくださいね![]()
「食事は愛」の日米クックです。
節分について
こんにちは![]()
2月3日は節分ですね![]()
節分の食べ物といえば…商売繁盛・無病息災を願って、
恵方に向かって食べる恵方巻や豆まき後に歳の数を
食べる豆などありますが、
各地域で様々な食文化があるようです![]()
*関西*
イワシ![]() ・・・鬼は焼いたイワシの臭いを嫌うと
・・・鬼は焼いたイワシの臭いを嫌うと
考えられているため、鬼除け・魔除けがあるとされる
*関東*
けんちん汁![]() ・・・冬の行事であることから、
・・・冬の行事であることから、
冷えた体を温める目的で食べる
*四国*
こんにゃく![]() ・・・食物繊維が豊富で便通がよくなることから、
・・・食物繊維が豊富で便通がよくなることから、
邪気を外に流す・身を清めるといった意味があるとされる
*信州・出雲*
節分そば![]() ・・・そばには厄を落とす・長寿を祈るといった
・・・そばには厄を落とす・長寿を祈るといった
意味があるとされ、1年を幸せに健やかに過ごせるようにと
願って食べるそのほかにも鯨を食べる地域、豆の代わりに
落花生で豆まきをする地域もあるそうです![]()
文化は多少違いますが、健康や幸福を願う事はどの地域も
共通していますね![]()
節分の日の献立にぜひ![]()
![]()
私の自宅玄関は節分仕様にしています。
行事ごとに飾りを変えると、季節感が味わえます![]()

「食事は愛」の日米クックです。

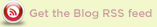

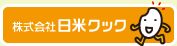

 締めは卵とチーズを入れてリゾットに。
締めは卵とチーズを入れてリゾットに。


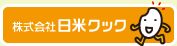
アーカイブ